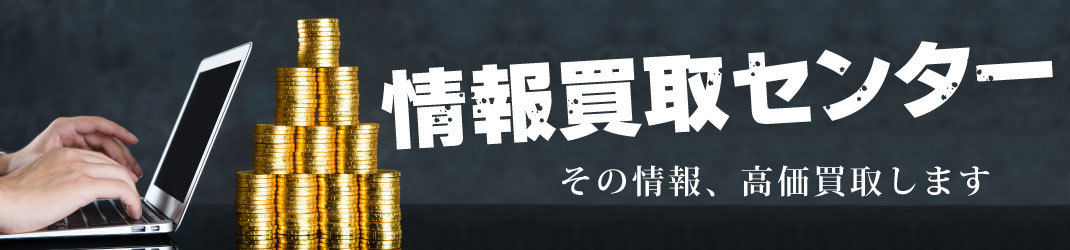信用情報に傷があると、金融機関の審査に通りづらくなり、「もう借りられないかもしれない」と感じる方もいるでしょう。特に「総量規制」という制度が壁となり、年収の3分の1を超える借入が制限される場面もあります。
しかし、この規制には除外や例外の枠が設けられており、条件を満たせば融資を受けられる可能性は十分にあります。ここでは、総量規制の基本的な仕組みと、対象外となる借入方法について詳しく解説します。
総量規制とは?
総量規制は、貸金業法に基づいて定められた制度で、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者からの借入総額が、年収の3分の1を超えないよう制限するルールです。これは、過剰な借入によって返済不能に陥ることを防ぐために設けられています。
総量規制の対象外となる借入方法
まず、総量規制の「除外貸付」に該当するものとして、不動産担保ローンや自動車担保ローンがあります。これらは、土地や車などの資産を担保にすることで、規制の対象外となり、高額な融資も可能になります。
また、有価証券を担保にしたローンや、売却予定の不動産に対するつなぎ融資も除外対象です。医療費の支払いを目的とした高額医療費貸付も、同様に規制の枠外で利用できます。
次に「例外貸付」として認められているのが、個人事業主の事業資金です。自営業者が事業目的で借り入れる場合は、総量規制の制限を受けません。さらに、親族の医療費や急な支出に対応するための短期・少額の融資(10万円以下・3か月以内)も例外として扱われます。
配偶者の同意があれば、夫婦の年収を合算して借り入れができる「配偶者合算貸付」も例外のひとつです。加えて、利率の引き下げや返済負担の軽減を目的とした借換えローンも、一定の条件を満たせば規制の対象外となります。
なお、銀行からの借入は、そもそも貸金業法の対象外であるため、総量規制の制限を受けません。
自治体や社会福祉協議会が提供する生活福祉資金貸付制度も、生活困窮者支援の一環として規制の枠外で利用可能です。
利用時の注意点
資金調達が可能であっても、返済能力を冷静に見極めることが重要です。無理な借入は、かえって生活を圧迫する原因になります。
また、貸金業者を選ぶ際には、貸金業登録番号の有無や金利の妥当性をしっかり確認しましょう。
違法業者(いわゆる闇金)との取引は、深刻なトラブルにつながる可能性があります。
借入の目的に応じて、制度を選ぶことも大切です。事業資金なのか、生活費なのか、用途に合った選択を心がけましょう。
まとめ
信用情報に不安がある場合でも、総量規制の仕組みを理解し、対象外の制度を活用することで、資金調達の道は閉ざされていません。焦らず、正確な情報をもとに、自分に合った方法を選びましょう。
当ブログはすべてフィクションです。
実践は自己責任でお願いします。
合わせて読みたいのはコチラ